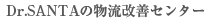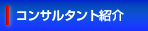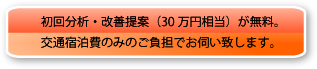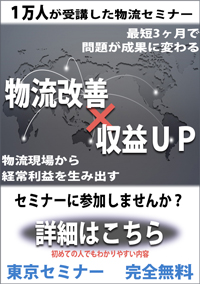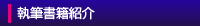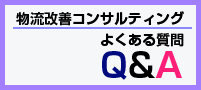物流改善セミナーレポート~輸送改革の進め方2016年6月15日~
2016年7月16日
“Dr.SANTAの物流診断”
改革のスタート地点は見える化。見えていない数値を見える化し、その上で作業の合理化を図る。輸送改革は無駄な経費を削減する改革。全ての改革はひとつひとつの作業を分析することからはじまる。そうした改革には熟練された視点と経験が必要。物流コンサルタントの平野さんの改革の強みは熟練された視点と経験。改革にダイレクトで取り掛かるためスピード感があり、経済効果を生み出すのも早いと評判。設備投資なしで結果を出すナンバーワン物流コンサルと言っても過言ではない。巨額な設備投資をする場合は導入時間や費用がかなり必要。しかし、平野さんのコンサル(物流改革)は設備投資を必要としない。

“設備投資なしで結果を出すナンバーワン物流コンサル“
平野さんの改革は以下の4つのポイントを実施することで数百万~億単位の経済効果をつくりだしている。
①在庫改革
②物流作業改革
③輸送改革
④物流クレーム改革
物流改革の中で一番改革が難しいのが輸送改革。この輸送改革は外部の運送会社の仕組みがわからないと難しい。しかし物流コストの中でダントツにコスト比率が高く、実は物流コスト40~50%が輸送費という会社が多い。しかし、輸送費の改革は難しく、できない会社が多いという。平野さんは運送会社の仕組みを良く理解している。平野さんの輸送改革は他の改革と組み合わせることで改革の相乗効果が生まれる。Dr.SANTA平野さんのコンサル(物流改革)の全体の経費削減の目安は売上げ金額の1%という驚異的な数値。
“輸送運賃を適正化する“
①無駄な配送費の削減
・貸切便の有効活用
・地域別個口別の運送会社選定
・梱包完了時間の前倒しによる適正運送会社の変更
・指定便の見直し
・共同配送の検討
②無駄な横持ち輸送費の削減
・ストック倉庫移動、センター間移動の削減
・共同横持ちの検討
③無駄な返品運賃の削減
・誤出荷の削減
・催事返品の削減
④調達輸送費(仕入金額)の削減
・調達物流の有効活用
輸送改革は、お客様が要望する物流サービスを維持しながら、輸送費を適正化することを目的としている。しかし、現実的には過剰サービスが非常に多く、最終判断は難しいところがある。また、多くの企業は自社便ではなく外部委託の運送会社を使用している。そのため、他の物流改革と違い「他力本願」のところがある。
“運賃のからくり地域で運賃の相場が変わる“
一般的には・・・
①運送会社のデポがあまり無い地域に物流拠点を作ると集荷を遅くまでやってもらえる運送会社が少なくなる。
②荷主は受注締め時間を早くして運賃下げる対応はおこなわなく。(得意先の物流サービスが下がる)そのため運送会社の選択肢が少なくなる。
③競合が少ないと運送会社は無理して値下げしなくても配送を任せてもらえるため運賃が高くなる傾向がある。
④保管費が安くなるだけで過疎地域に物流センターを構築した場合、保管費は安くなるが運賃は高くなり、結局は物流コストが高くなる可能性がある。
⑤運賃が高くなるだけでなく人口が少ない地域では人の集まりが少なくなり。時給を上げないと人のレベルが低いメンバーの比率が高くなるため物流品質が保てなくなる。
“輸送費の概要調査”
輸送改革を推進する上で第1段階は運賃の現状の把握である。基本的には売上げ金額と比較し運賃が何%かを掴む必要があるが輸送方法の内容によって対策が違うため分けて集計をする。
・輸送費集計 (見える化)
・現状輸送の簡易把握 (見える化)
・緊急出荷運賃分析 (分析)
・地域別出荷運賃見積もり比較をつくる(重要)
・ピボットテーブルを活用した運賃分析 (分析)
・コース便の調査 (見える化)
・配達件数調査 (見える化)
・貸切便分析表 (見える化)
輸送費用全体の数字を見える化し中身を検討できる状態にすることで難しい改善も進めて行けるようになる。その結果100万200万といった金額の経費削減が可能となる。
《改善実績》
・運賃の5%のコストを削減
・年商1%相当の削減
・物流作業効率が200%へ向上
・クレーム発生率が10分の1に
《改善のポイント》
①緊急出荷の抑制
・自社原因の緊急出荷
・緊急出荷の日常化 (※過剰サービス)
②少量個口出荷に判断基準の見直し
・物流変動による運送会社の選定ができていない
③地域別輸送会社の見直し
・運送会社の判断基準ができていない
④指定便の原因分析ができていない
⑤貸切便の配送の見直し
・過剰サービスが発生している
・配達便検証ができていない
⑥返品の削減
・返品運賃の見直しができていない
“輸送改革の勘違い”
輸送改革は運送会社の見直しではない。「輸送改善=運賃削減」と思い込んでいる。運賃削減は運送会社に値引き要請するしか方法が思いつかない。色々と案を出しても受け入れてもらえなければ意味がない。運送会社から値引きができないと言われている。運送会社からも提案もない。運送会社が変わると「納品遅れクレーム」が発生する可能性があるため変えたくない。だから、輸送改革がこれ以上できない会社が多い。
※輸送改革には在庫改革が必要で在庫改革をしないと外部倉庫がなくならない。よって輸送費が発生する。
※輸送改革には作業改革が必要で倉庫内が散らかっていると作業効率が悪くなる。よって出荷が遅れる。
※輸送改革は他の改革と一緒にやることで高い効果を生み出すことができる改革。
・在庫改革・作業改革・輸送改革・物流クレーム改革
全ての改革を実行し相乗効果を生み出すことが平野さんの輸送改革。勿論簡単な改革ではないが社員全員で取り組み。完成した後には、結果もノウハウも企業に残り続ける。自社の強みを手にした物流現場は生まれ変わり、効率的な作業で経済効果を生み続ける。強い物流現場を社員やパートさんたちの手で維持管理運営できるようにすることが、本当の物流改革だと平野さんは考える。
ライター紹介:かわしま
1973年東京生まれ 専門性の高いサービスに特化した記事を数多く執筆している。
新刊のご案内:2014年7月

物流改革の手順(出版文化社)
1,890円

3ヶ月で効果が見え始める物流改善
【現状把握編】
(プロスパー企画)
1,890円